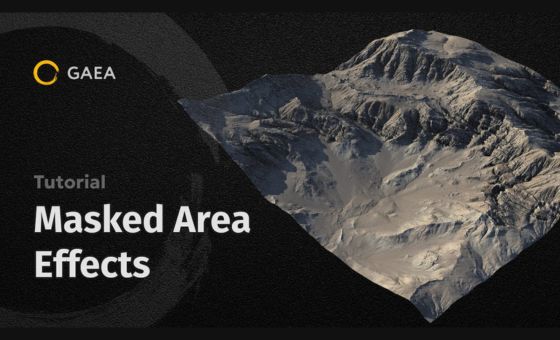はじめに
Thermal 2 は「熱侵食(風化+重力崩落)」をシミュレートし、鋭い稜線を丸めつつ、麓に崖錐(talus)を形成します。Erosion 2(水理侵食)が谷やガリーを刻むのに対し、Thermal 2 は形を保ちながら“崩れ落ちる”方向に地形を変えるのが特徴です。本記事では主要パラメータ、Erosion 2 との連携(選択的降水・傾斜バイアス)、アートディレクションの勘所と実務での微調整手順を、解説します。
Thermal 2 入門:形を保つ侵食のコツ
Thermal と Hydraulic の違い(要点)
Thermal と Hydraulic の違い(要点)
Thermal 2
温度差や凍結融解で岩が割れ、重力で足元へ堆積します。稜線は丸くなり、崖に崖錐が溜まります。
温度差や凍結融解で岩が割れ、重力で足元へ堆積します。稜線は丸くなり、崖に崖錐が溜まります。
Erosion 2
降水・流出で谷やチャネルを掘削し、土砂を運搬します。
降水・流出で谷やチャネルを掘削し、土砂を運搬します。
両者を段階的かつ選択的に使い分けることで、山肌から谷底まで自然な整合が取れます。
Thermal 2 の主要パラメータ(短縮リファレンス+使いどころ/注意点)
Thermal 2 の主要パラメーター(短縮リファレンス+使いどころ/注意点)
-
Duration(継続時間):長いほど歳月が進み、丸みと堆積が増加します。
・狙い:全体に年季を与えます。注意点:やり過ぎるとシルエットを損ないます。迷ったら0.4–0.6付近から始めると良いです。 -
Strength(強度):1ステップの崩落量です。短時間で効果を強めたいときに上げます。
・狙い:結果を早く確認できます。注意点:粗い崩れ方になりやすいので、強めの場合は Feature Scale を上げて大きな形状(シルエット)を保護すると良いです。 -
Anisotropy(異方性):平滑化の強さ/形状保存の度合いを決める最重要パラメータです。
・低い:原形を保ちやすいです。/高い:均しが強く、崖錐も顕著になります。
・コツ:まず 0–0.3 で開始し、必要分だけ上げます。注意点:高すぎると“粘土細工”のように見えることがあります。 - Talus Angle(崖錐角):堆積の傾きを決めます。高い=急で短い堆積(巨礫感)/低い=緩く広がる(砂利〜土砂)
まずは 5 分で試す:最小セットアップ
まずは5分で試す:最小セットアップ
- ベース地形に Thermal 2 を接続します。
- 初期値の目安: Duration 0.4 / Strength 0.5 / Anisotropy 0.2 / Talus Angle 35 / Feature Scale 15 / Sediment Removal 0.2 です。
- チェック:断崖が埋もれていないか、峰の稜線が別物になっていないかを確認します。
- 丸すぎる場合: Anisotropy を下げ、 Feature Scale を上げます。 必要に応じて Talus Angle を上げ、緩斜の広がりを抑えます。
- 粗く見える場合: Strength を下げ、 必要であれば Duration を上げて時間で効かせる側に寄せます。
Thermal 2 × Erosion 2:現実的な連携レシピ
Thermal 2 × Erosion 2:現実的な連携レシピ
狙いは「崖は崩れ落ち、谷は水で刻まれる」という役割分担の再現です。
手順例(3パス)
- Erosion 2(Pass1) 主要谷筋と一次堆積を作成し、Wear/Flow/Deposits を取得します。
-
Thermal 2(Pass2) 稜線や急斜面を丸めて崖錐を形成します。
- ディテールを温存したい場合は、Anisotropy 0–0.3、Feature Scale 15–25 を目安にします。
-
Erosion 2(Pass3) 選択的降水マスク駆動で必要な場所だけ雨を降らせます。
- Wear(侵食量) マップを降水マスクに使用します(例:Erosion_2 の Wear 出力)。
- 傾斜バイアス(概念としての傾斜抑制)を使い、急斜面への降水を弱めて水理で削らせないようにします(崖は主に Thermal の領域にします)。
- ※傾斜抑制は機能名ではなく概念です。実装は Slope バイアスやマスクで行います。
配線のコツ(迷いやすい箇所)
配線のコツ(迷いやすい箇所)
- Wear を取り出したら Auto Level で可視化し、Erosion 2 の precipitation(降水)マスクへ接続します。
- 崖だけ乾かす場合は Slope マスクで急斜面を除外します。
- 稜線は乾き、谷底だけ濡らす場合は Altitude マスクで下層を優先します。
-
適用順の入れ替えも試す価値があります。
- 先に Thermal:全体を柔らかくし、その後に水が talus を二次加工します。
- 先に Erosion:河道を先に刻み、その後に Thermal で谷壁を崩して自然な緩斜にします。
合成のポイント
合成のポイント
- 地形を削らず足すだけにしたい場合は、Combine(旧 Mixer) の 「Max」 で上流レイヤーに堆積を重ねます (破壊ではなく加算的に合成できます)。
- 足し過ぎに見える場合は、Combine の入力側でレベル調整 (Auto Level/Shaper など) を行い、再度 Max でブレンドします。
まとめ
まとめ
- Thermal 2 は、山肌に年輪のような風化と崖錐(talus)を素早く与えるノードです。
- Anisotropy × Feature Scale を調整して、大きな形状(シルエット)を保ちつつ必要なだけ平滑化します。
- Erosion 2 では選択的降水(傾斜・標高などのマスク)を使い、「水が当たる/当たらない」領域を明確に分けます。
- 仕上げで削らず足す合成にする場合は、Combine(旧 Mixer)= Max を使い、堆積側(加える側)を正規化(Auto Level や Clamp 併用)して過度な持ち上がりを防ぎます。
- この流れにより、遠景は堂々、近景はディテール豊富な地形を、実制作でも扱いやすい短いノードチェーンで実現できます。